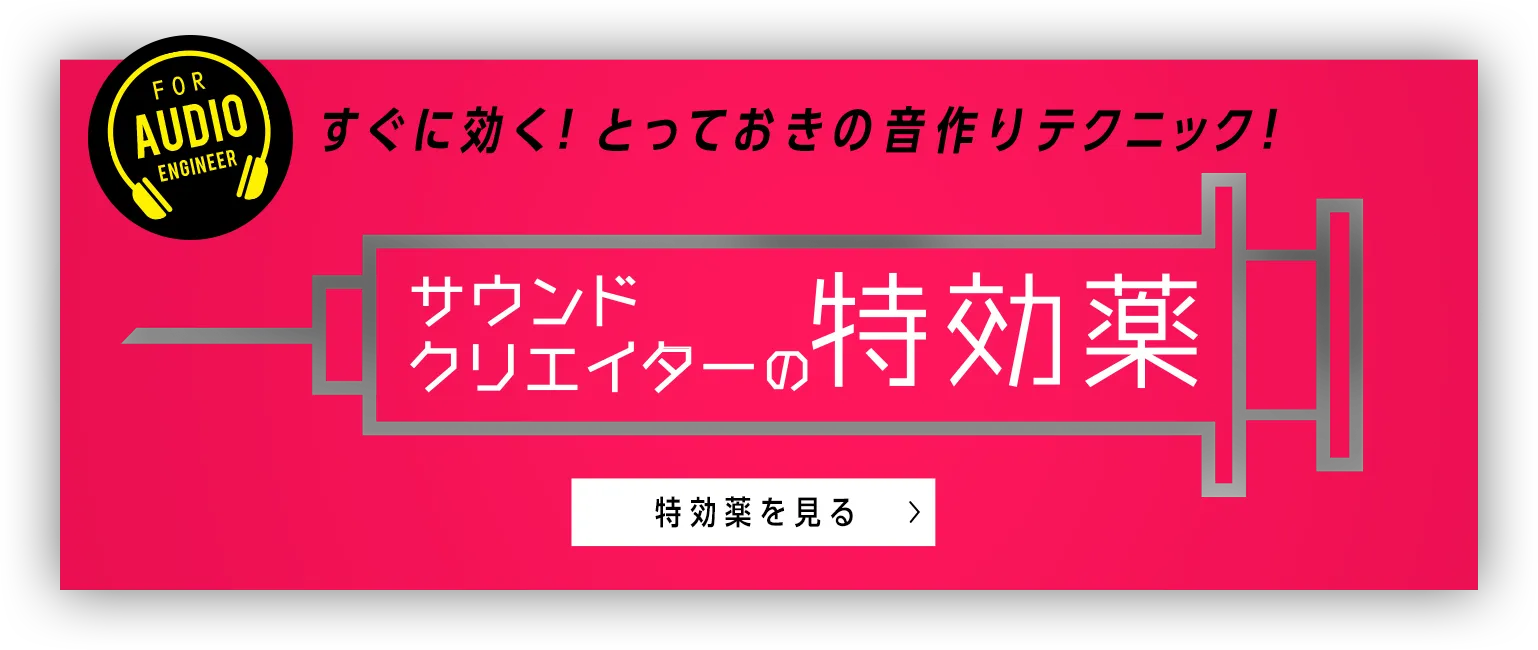Story #02
「AIM CUP」らしさを求めて
eSportsをもっと多くの人々へ
w/ 株式会社Trigger 代表取締役 安齋 拓実
eSportsの大会(オンラインコミュニティ大会) 「AIM CUP」を開催・運営されている株式会社Triggerの代表取締役である安齋 拓実さん(以下、安齋さん)が、「AIM CUP」のBGMを作成されたいということで、株式会社アットチュード(以下、アットチュード)にご依頼いただいたことから、本プロジェクトがスタート。
無事にBGMも完成し、大会でも継続的に使用いただいています。
今回は、安齋さんと本プロジェクトを担当したアットチュードメンバーKyrieとともに、大会・BGMにかける想いからeSportsの未来まで・・・さまざまなお話を聞かせていただきました。
WORKS

「AIM CUP」
AIM CUP内BGM(イベントBGMの制作)
作曲・メイン進行:Kyrie
大会公式サイト:https://aimcup.jp/

「AIM CUP」
株式会社Triggerが主催するeSportsの大会(オンラインコミュニティ大会)。
ゲームタイトル「VALORANT」「OVERWATCH2」の2タイトルで開催されており、本格的な競技シーンだけでなく初心者の方でも楽しめる大会を目指している。
そのイベント内で流れる各種BGMを株式会社アットチュードが制作。
株式会社Trigger 公式サイト
https://trigger-99.com/

「eSportsが好き」という
共通項から
新しい「AIM CUP」の音を
- 安齋さん、株式会社Triggerでは、どのような事業を展開されていますか?
-
安齋さん
弊社は、2021年から開始した「AIM CUP」運営をはじめとし、コンサルティングなども行うeSports事業と、Z世代を中心としたVTuber、TikToker、アイドル、コスプレイヤー、声優、YouTuberなどのCasting事業という2つの軸で、活動しています。
eSports事業をはじめたきっかけは、大学3年生のときに、周囲が就職活動をはじめなければという雰囲気のなかで、私は自分でなにかをしてみたいと考えるようになりました。そこから、eラーニングに関連した事業を考えるようになり、東京都が運営しているインキュベーション施設で無料相談したときに、「対象となる市場をもっと狭めたほうがいい」とアドバイスをいただきました。
そこから、もともとゲームが好きだったり、eSportsの市場はこれから広がっていくという話を耳にしたり。そんな状況から、この事業がはじまりました。
最初は、eSportsのゲームを習いたい人と教えたい人のマッチングサービスをはじめたのですが、そこから事業を展開をするなかで、「eSportsのコミュニティ大会が少ないよね」という話になり、大会を開催するようになりました。 - 今回、アットチュードへBGM制作を依頼されたきっかけは何でしたか?
-
安齋さん
「AIM CUP」を続けていくうえで、大会のロゴや見せ方をよりよいものにリニューアルしていこうというタイミングがあって。そのときに、それならBGMも!と思い、アットチュードさんへお電話しました。
アットチュードさんは別の大会で協賛をされていたことから、お名前や事業内容については知っていたのですが、お電話はしてみたものの、「あれ、どんな依頼の仕方をすればいいのかな」と思ってしまいました。
そう迷っている間に、電話がつながり、その後20、30分くらいお話ししました。お話しするなかで、依頼の仕方がわからない私に対しても、制作のイメージをすごくクリアにしていただきました。 -
Kyrie
お電話のなかで、全体的な流れや制作する曲数のイメージも決めていきましたよね。
-
安齋さん
はい。そのほかにも、ゲームやeSports自体のお話を電話中にしていて、「この人もゲーム、eSportsが好きなんだな」と思えたことが、アットチュードさんへ依頼しようと思った一番の決め手です。
-

セオリーではないやり方で
“没入”できる「AIM CUP」
ならではの世界観を
- Kyrieさん、実際に依頼を受けて、BGMを制作するときに、どんなことをイメージされましたか?
-
Kyrie
通常の制作時は、依頼を受けたあとで、たとえば過去の大会の様子を見てみるなど、ほかの大会の様子などをすごく調べたりもするのですが、今回の場合は、自分もFPS(「First Person Shooter」の略で、一人称視点のシューティングゲーム)をプレイすることもあって、すごくイメージがつきやすかったんですよね。
たとえば、「VALORANT」ならEDM(Electronic Dance Musicの略で、電子音を使ったダンスミュージックを指す音楽ジャンルの総称)寄りの音が合いそうな世界観だなとか、意外なほどに迷うことなく制作をすることができました。 - 今回のBGMを制作するうえでのポイントはどんなところでしたか?
-
Kyrie
大会のBGMは、あくまで大会のBGMで、ゲーム内のBGMとは違うものなんですよね。まずはゲームが主役でなければいけないし、プレイの合間、インターバルに流れる曲は、解説の邪魔はしないように、でも、次の展開に向けてテンションを上げていく。
あとは、エンディングの曲については、もう結果も出たあとのノーサイドな状態なので、爽やかな世界観にする、というふうに、大会中に流れるポイントや状況に合わせて、BGMの印象を変えていくというのがセオリーとしてあります。
でも、今回の「AIM CUP」については、ゲームタイトルを作成している会社が行う公式大会ではなく、独自の大会だからこそ、セオリーを守ることよりも、「AIM CUP」やゲームタイトルの世界観を一貫するほうが出場者も観戦者も楽しいかなと考えたところは、大きな考え方としてあります。
たとえば、観戦者は試合の合間などのBGMを結構長いこと聞くので、そういった場面場面でゲームタイトルの世界観から離れたりしないほうがいいなと考えていて。
だから、今回のBGMは、大会開始から終了まで、試合の合間などもふくめて、すべてゲームタイトルの世界観でシームレスにつながっていく展開にして、試合だけでなく大会全体に没入してほしいと思って、それぞれのBGMを作成しました。 -
安齋さん
本当に、ありがとうございます。仕上がりの曲を聴いた際には、感動というか圧倒されて。リテイクをお願いさせていただくような場面は一切なかったです(笑)
- リテイクが0回なのは、すごいですね!
Kyrieさん、そのほかにも、なにかポイントがあれば教えてください。 -
Kyrie
そのほかには、サウンドの話でいうと、曲のなかに一部アコースティックギターの生音を入れているパートがある、というのもあります。
曲の途中で、ギターの音が結構映える場面があって、そこだけ、アコースティックギターを生演奏した音を入れました。
これはほかの作品や仕事でもそうなのですが、やっぱり、生の音とそうでない音は聴くと違いは出てくるので、なるべく自分たちで弾ける部分は弾いた音を入れることで、立体感が出ますし、今回の大会でいえば、デジタルな世界となるゲームのなかにも、アナログな部分を入れて、人間が行っている大会なんだよ、というのを表現するというか (笑)
あとは、アットチュードは全員楽器のプレイヤーでもあるので、やはりそこはアットチュードだからこその魅力として、適しているタイミングでは生演奏も入れていきたい、ということもあります。 -
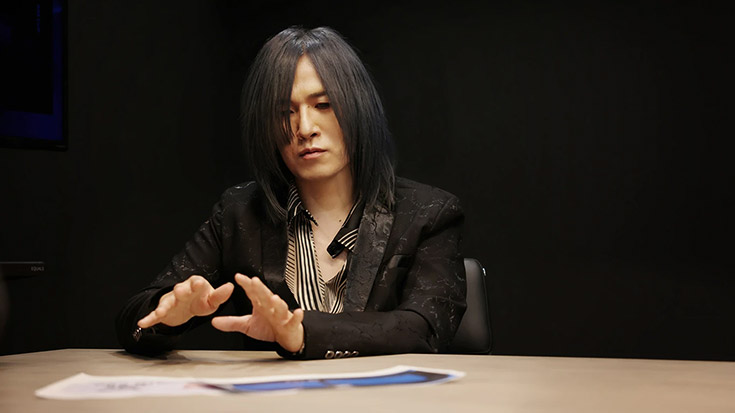
いろいろな選手・人・
会社と手を組んで
リアルな大会を開催してみたい
- 安齋さん、eSportsや大会などで、今後やってみたいことはありますか?
-
安齋さん
いま運営している大会はオンラインでの大会になるので、今後はオフラインでの大会、実際に集まって実施する大会を開催してみたいなと思っています。
もちろん、オフラインになる分、関わる人だったり機材だったり、実施に至るまでの準備から実施までのハードルがまたひとつ上がるので、いろいろな会社さんとの協力が必要になるとは思っているのですが、実現して、オンライン・オフラインに関わらずたくさんの大会を開いていきたいと思っています。 -
Kyrie
リアルな大会のスタッフの動きを見ていると、開催前のチェックとか相当大変そうですもんね・・・。
-
安齋さん
はい(笑)あとは、今も大きい公式の大会だと、大会を俯瞰しているカメラとプレイしている選手視点のカメラが切り替わるなど、いろいろな演出上のことを考えると、大変だとは思っています。
-
Kyrie
オンラインとオフラインだと、BGMのつくり方も変わりますよね。まずはその場にお客さんがいるので、聴くボリュームが全く変わりますし、作曲するうえでも、オンラインよりも臨場感を意識したものが欲しくなると思います。
- Kyrieさんは、今後、eSportsのイベント・大会の依頼を受けたときにやってみたいことはありますか?
-
Kyrie
そうですね、今後もっとeSportsのイベント・大会が増えていくにあたって、それぞれのイベントのカラーをもっと出していくことが大切になると思っていて。
ゲームタイトルに寄せるだけでなく、主催者側の意図や視聴者層の好みも汲み取りながら、両方それらをしっかりつなぎとめて、その大会らしさが出るサウンドにしたいですね。
今も、個人で開催されている大会、大きい公式大会、賞品がちょっとおもしろい大会、といろいろとあるので、そういったそれぞれの大会の特色をとにかく見て学んでいます(笑) -

未来のeSportsのために
「AIM CUP」“らしさ”を
考える、追求する
- ちょっと飛躍して大きなテーマの話をするのですが、eSportsの未来はどうなると考えていますか?
-
Kyrie
ぼくは観戦者として、今のeSportsの大会を見る感覚は、一昔前で言う野球中継を見ているような感覚なんですよね。まさに、リアルなスポーツ観戦と同じ感覚というか。
そういう感覚になれるようになったのは選手達の競技レベルの上昇はもちろん、大会放送のクオリティ上昇に起因する部分も大きいと思っています。だから、それだけ素晴らしいものだし、もっともっと市民権を得て、大きな文化になっていったら、相乗的にもっとeSportsの大会も楽しくなるだろうなと思っています。 -
安齋さん
おっしゃる通りで、この前、テレビでも大会が放映されていました。
eSportsにまつわることでも、日本は海外よりも5年くらい遅れているという話をよく聞くのですが、それでも、主要なゲームタイトルの決勝が日本で開催されることも出てきて、日本の熱量もすごく高まって、世界最高水準と言ってもいいのではと思うくらいになっているので、この機会を活用して、eSportsを好きになってくれる人を増やしたいですよね。
今も「ゲームだもんね」という視点で、eSportsに興味を持つ入口にもいない方も多いので。
それこそ、弊社でも、「どういう人を招待・起用したらいいか」だったり、「どういう内容だったらいいか」や、興味のない人たちが「どういう大会だったら見たいと思うか」という点は、もっと突き詰めていきたいです。
AFTERWORD
「あなたのための、すべての音を」という理念には、決まりきっている道を辿るのではないという意味が込められていると思う。だから、セオリーではない選択肢を選び、BGMを制作できた。また、これからどんどんと道なき道をつくっていくeSportsというジャンルでも、安齋さんと足並みを揃えて伴走できるのだなと感じた。
BGMのクオリティはもちろんだが、クライアントとなる安齋さんとアットチュードメンバーが、インタビューでも、過去の制作エピソードにとどまらず未来を語り合える関係性になっていること自体が、このプロジェクトで実った価値そのものだと思う。

今後、eSportsはもちろん、eSports以外の事業でもいろいろなことを展開していきたいと話す安齋さん。
私たちアットチュードも引き続き、安齋さん、株式会社Triggerさん、「AIM CUP」を応援し続けるとともに、安齋さんと同じく挑戦を続けていきたいと思います。